観光業界のSEO対策|集客強化に効く実践ノウハウ
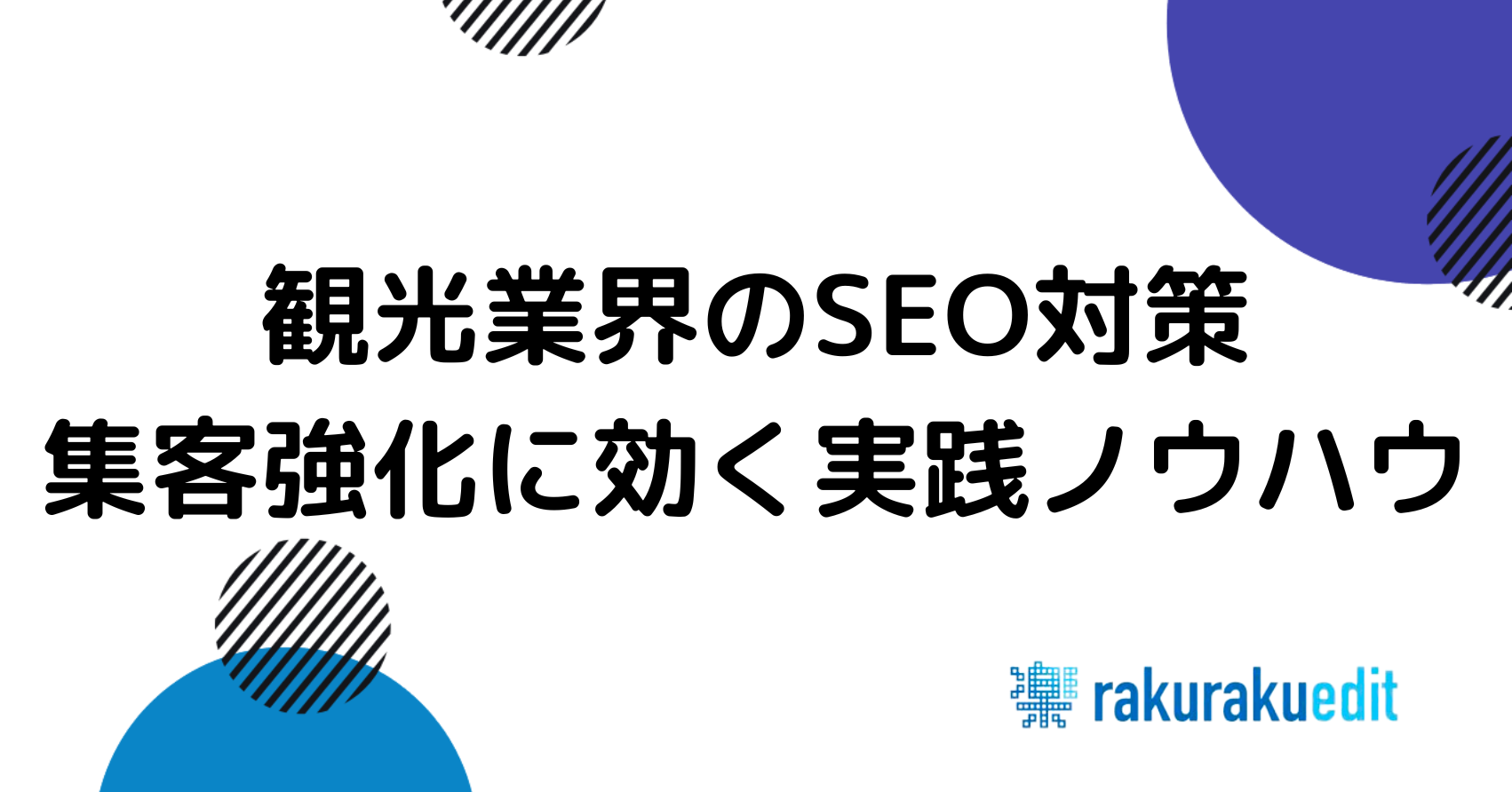
コロナ禍からの回復やインバウンド需要の復活が進む観光業界。今、安定した集客を実現するために不可欠なのが「SEO」です。旅行者の情報収集がスマホでの検索中心となった現代、検索エンジンでいかに自社の魅力を見つけてもらうかが勝負の分かれ目となります。
本記事では、観光業界に特化したSEO対策の実践ノウハウを具体的に解説。集客力を最大化し、競合との差別化を図るヒントを提供します。
観光業界におけるSEOの重要性
観光業界でSEOが重要視されるのは、旅行者の行動様式の変化と収益構造の変化が背景にあります。旅行計画の全てが検索から始まる現代において、検索結果に表示されない施設やサービスは存在しないのも同然です。
OTAへの手数料が経営を圧迫する中、SEOで自社サイトの集客力を高め、直接予約を増やすことが利益率改善の最重要課題となっています。ここでは、「旅行者の検索行動の変化」「直接予約の必要性」「ブランディング効果」という3つの観点から、SEOの重要性を詳しく解説します。
観光客の検索行動と情報収集の変化
現代の旅行計画は、検索から始まります。旅行者の行動は、一般的に以下の3つのフェーズに分けられます。SEO対策を考える上では、それぞれの段階でユーザーが何を求め、どのように検索するかを理解することが不可欠です。
旅マエ(たびまえ): 旅行に出かける前の、情報収集や計画、予約を行う段階です。行き先の検討から、宿泊施設や交通手段の予約、現地の観光スポット調査などが含まれます。
旅ナカ(たびなか): 旅行中の段階です。現地での移動中や滞在中に、リアルタイムで情報を検索します。「現在地 周辺 ランチ」や「〇〇(観光地) 混雑状況」など、即時性の高いニーズが特徴です。
旅アト(たびあと): 旅行が終わった後の段階です。旅行の思い出をSNSでシェアしたり、次の旅行計画を立て始めたりする行動が含まれます。
これらの各フェーズにおいて、検索行動は中心的な役割を果たします。特に「旅マエ」では、「週末旅行 おすすめ」といった漠然としたインスピレーションを探す検索から始まり、次第に「箱根 温泉 日帰り 個室」といった具体的な比較検討の検索へと移行します。「旅ナカ」では、その場のニーズに基づいた即時性の高い情報が求められ、検索結果の利便性が直接顧客満足度に繋がります。
テキスト検索だけでなく、YouTubeで現地の雰囲気を動画で確認したり、Instagramのハッシュタグでリアルな口コミを探したりと、情報収集チャネルは多様化していますが、その起点となるのはGoogle検索であることが多いのです。
オンライン予約主流化によるSEO施策の必要性
OTA(Online Travel Agent)の普及により、オンライン予約は完全に主流となりました。多くの事業者がOTAからの集客に依存していますが、その代償として10~20%以上にもなる手数料の負担は経営を圧迫します。
さらに深刻なのは、OTA経由の顧客は施設の「ファン」ではなくOTAの「ファン」であるためリピートに繋がりにくく、最も重要な顧客データを自社で蓄積・活用できない点です。
自社サイトにSEO対策を施し、直接予約(ダイレクトブッキング)の比率を高めることは、これらの課題を解決する特効薬となります。手数料分の利益が確保できるだけでなく、顧客情報を自社で管理することで、メルマガ配信や特別オファーによるリピーター育成が可能になります。
SEOは、目先の集客施策という側面だけでなく、LTV(顧客生涯価値)を最大化し、持続可能な収益基盤を築くための重要な経営戦略なのです。
競合との差別化とブランディング強化の観点
検索結果の画面は、ユーザーが最初に目にするデジタル上の「店舗の棚」です。自社の公式サイトが魅力的なタイトル・説明文で表示されることが、強力なブランディング活動となります。
「この地域といえば、この施設(サイト)」という第一想起を獲得できれば、ビジネスは非常に有利に進みます。特に観光業では、価格以外の「体験価値」が重視されます。
公式サイトのSEOコンテンツを通じて、施設の歴史やコンセプト、スタッフの想い、地域文化との関わりといったストーリーを深く伝えることで、単なるスペック比較に陥りがちなOTAとは一線を画した独自のブランドイメージを構築できるのです。
観光業向けのキーワード戦略と選定方法
SEOの成功は、ユーザーの多様な検索意図を的確に捉えるキーワード選定から始まります。観光業界では特に、地域性、季節性、目的といった多角的な視点での戦略が求められます。ここでは、観光業界でSEO上位表示を獲得するための、キーワード選定や具体的な対策について解説します。
地域名+観光地名のロングテール対策
多くのユーザーは、「地域名」と「目的」を組み合わせて検索します。例えば「箱根 温泉」のようなビッグキーワードで上位表示を狙うのは競争が激しく困難ですが、「箱根 温泉 日帰り 個室」「箱根 温泉 貸切露天風呂付き」といった、より具体的で詳細な3語以上の「ロングテールキーワード」であれば、競合は格段に減り、上位表示の可能性が高まります。
これらのキーワードで検索するユーザーは目的が非常に明確なため、コンバージョン率(予約率)が非常に高い傾向にあります。ロングテールキーワードを見つけるには、Googleの検索窓に表示されるサジェスト機能や、Yahoo!知恵袋のようなQ&Aサイトでユーザーの生の悩みを調査する方法が有効です。
また、自社の予約担当者やフロントスタッフが顧客からよく受ける質問の中にも、貴重なキーワードのヒントが隠されています。「ペットと泊まれる宿 〇〇」「御朱印巡り モデルコース 〇〇」といったニッチなニーズに応えるキーワードを発掘し、それぞれに特化したコンテンツを作成することが、着実な成果に繋がります。
季節・イベント・目的別キーワードの活用
観光需要は、季節や地域のイベント、旅行者の目的に大きく左右されます。これらの時節性やニーズを捉えたキーワード戦略は、爆発的なアクセス増をもたらす可能性があります。そのためには、年間を通じた「SEOコンテンツカレンダー」の作成が非常に有効です。
春には「〇〇(地名) 桜 見頃 2025」「お花見 おすすめスポット 関東」、夏には「〇〇(地名) 花火大会 見える宿」「夏休み 子連れ 旅行」、秋には「〇〇(地名) 紅葉 ライトアップ」、冬には「〇〇(地名) スキー場 オープン情報」といったキーワードが考えられます。
重要なのは、需要が高まる1~3ヶ月前にはコンテンツを公開しておくことです。検索エンジンがページを評価し、順位が安定するまでには時間がかかるため、需要のピークに合わせて先行して情報発信を行う計画性が成功のカギとなります。
多言語SEOを意識したインバウンド対策
急速に回復する訪日外国人観光客(インバウンド)の集客には、多言語でのSEO対策が不可欠です。しかし、これは単に日本語ページを機械翻訳するだけでは全く不十分です。
国・地域ごとに主流の言語、検索エンジン、文化、旅行スタイルが大きく異なることを理解し、それぞれに最適化された「ローカライゼーション」を行う必要があります。
英語圏のユーザーは”Japan travel guide” “things to do in Tokyo”のように情報収集型の検索を好み、中国大陸では検索エンジン「Baidu」で”日本自由行攻略”(日本の個人旅行攻略法)や”东京必买清单”(東京で必ず買うべきリスト)といったキーワードが使われます。
台湾・香港の繁体字圏では”東京景點”(東京の観光スポット)”京都住宿推薦”(京都のおすすめ宿)といった表現が一般的です。
それぞれの国・地域で実際に使われているキーワードを調査し、現地の文化やニーズに合わせたコンテンツを作成することが重要です。また、技術的には、各言語ページがどの国・地域向けかを示すhreflangタグを正しく実装し、Googleにサイトの多言語構造を正確に伝える必要があります。
インバウンドSEO対策ガイド|訪日外国人集客を成功させる方法
MICE・団体旅行など需要別キーワードの狙い方
一般的な個人観光客だけでなく、MICE(会議、研修旅行、国際会議、展示会)や社員旅行、サークル合宿といった特定の需要を持つ団体客は、予算規模が大きく非常に魅力的なターゲットです。
こうしたユーザーは、「会議室 東京 大人数」「研修旅行 おすすめプラン」「キックオフイベント 会場」といった、よりビジネス寄り、あるいは目的が明確なキーワードで検索します。
彼らが求めているのは、単なる施設の魅力だけでなく、会場の収容人数、プロジェクターや音響設備といった機材のスペック、ケータリングサービスの有無、分科会のための小部屋の数、周辺の宿泊施設との連携、アクセス、そして何よりも過去の受け入れ実績です。これらの情報に特化した専用のランディングページ(LP)を作成し、必要な情報を網羅的に掲載することが重要です。
導入事例として過去に利用した企業名やイベントの様子を写真付きで紹介できれば、信頼性は格段に高まります。明確な問い合わせフォームや専用の見積もり依頼ボタンを設置し、スムーズなコンバージョン導線を設計しましょう。
SEOに強いコンテンツの作成と運用ポイント
キーワード戦略に基づき、ユーザーの検索意図を完璧に満たす、質の高いコンテンツを作成・運用することがSEOの核となります。
ここでは、訪問前の疑問解決から予約(CV)を後押しする旅行プラン、視覚的に魅力を伝える写真・マップ活用、インバウンド需要に応える多言語ページまで、ユーザーと検索エンジンの両方から評価されるコンテンツ作成・運用ポイントを具体的に解説します。
コンテンツSEOってどんな施策?必要な手順やメリット・デメリットについて解説!
訪問前の疑問を解決するQ&A型記事
旅行者は、特に初めて訪れる場所に対して、多くの疑問や不安を抱えています。
「最寄り駅からのアクセス方法は?」「駐車場は予約が必要?」「雨天でも楽しめるアクティビティはある?」「アレルギー対応の食事は可能か?」といった、顧客から頻繁に寄せられる質問(FAQ)は、コンテンツの宝庫です。
これらの疑問に先回りして答えるQ&A形式のコンテンツは、ユーザーの不安を解消し満足度を高めるだけでなく、SEO上も非常に有効です。
作成手順としては、まず社内(予約担当、フロント、電話応対者など)でよくある質問をリストアップし、それらを「アクセス」「食事」「施設設備」などのカテゴリに分類します。各質問に対して簡潔かつ分かりやすい回答を用意し、必要に応じてより詳細な情報が書かれたページへ内部リンクを設置します。
このQ&AページにFAQPageスキーマという構造化データを実装することで、検索結果上で質問と回答が直接表示される(リッチリザルト)可能性が高まり、クリック率の大幅な向上が期待できます。
体験記事・旅行プランの提案でCVを促進
観光地やアクティビティの魅力を伝え、予約や問い合わせといったコンバージョン(CV)へと繋げるには、ユーザーが「ここに行きたい!」「この体験をしてみたい!」と強く感じるような、具体的な利用シーンを想像させるコンテンツが重要です。単なる施設のスペック紹介に留まらず、ユーザーが自分ごととして捉えられるストーリーを提示しましょう。
効果的なコンテンツの例として、ペルソナに合わせたモデルコースの提案が挙げられます。30代の子連れファミリー、20代のカップルなど、ターゲット顧客のペルソナを設定し、そのペルソナに向けて、「週末モデルコース」や「記念日におすすめの1泊2日プラン」などを提案する記事を作成します。記事には、具体的なタイムスケジュール、立ち寄りスポット、おおよその予算感を盛り込み、読者が旅行全体をイメージできるように構成することが重要です。
また、臨場感あふれる体験記事も効果的です。スタッフが実際に施設やアクティビティを体験し、その魅力や楽しみ方をレポート形式で紹介することで信頼性が高まり、ユーザーの興味を強く惹きつけます。
コンバージョンへの導線としては、記事の最後に、関連する宿泊プランや予約ページへのリンク(CTAボタン)を分かりやすく設置します。ユーザーの感情が高まった瞬間を逃さず、スムーズにコンバージョンへと誘導しましょう。
現地写真やマップ活用による視覚訴求
観光地の魅力、施設の雰囲気、料理の美味しさは、文字だけでは決して伝わりきりません。ユーザーの五感に訴えかける視覚的な情報は、コンテンツの価値を飛躍的に高めます。
プロのカメラマンが撮影した高解像度で魅力的な写真をふんだんに使用しましょう。晴天時の外観だけでなく、雨の日の風情ある写真、夜景、季節ごとの景観など、様々なシーンの写真を用意することで、サイトを訪れるたびに新たな発見があるように演出できます。
また、基本的なSEOとして、すべての画像にはalt属性(代替テキスト)を設定し、「箱根の旅館から見える紅葉の景色」のように、その画像の内容を説明するキーワードを含めることを忘れないでください。
さらに、Googleマップをページに埋め込み、施設へのアクセスや周辺の観光スポットとの位置関係を視覚的に示すことは、ユーザビリティを大きく向上させます。ユーザーが地図上で直感的に距離感や利便性を把握できることで、「ここなら計画が立てやすそうだ」という安心感を与え、サイトからの離脱を防ぐ効果があります。
訪日外国人向けの多言語ページ展開
インバウンド集客を本格的に行うなら、専門性の高い多言語ページの展開が必須です。
ここで最も重要なのは、「翻訳(Translation)」と「ローカライゼーション(Localization)」の違いを理解することです。単に日本語を他言語に置き換えるだけでなく、対象国の文化、慣習、価値観に合わせてコンテンツ全体を最適化する必要があります。
例えば、食事のハラル対応やベジタリアンメニューの有無、礼拝スペースの情報はイスラム圏のユーザーにとって極めて重要です。また、欧米では一般的でない「旅館の布団」の仕組みを丁寧に説明したり、室内での靴の着脱といった日本の習慣を解説したりすることも親切です。通貨表記や日付の書式を現地に合わせる、現地の人が自然に感じる言葉遣いで文章を作成するといった細やかな配慮が、海外ユーザーからの信頼を勝ち取ります。
観光業界で有効なテクニカルSEO施策
良質なコンテンツを検索エンジンに正しく評価してもらうためには、サイトの技術的な基盤を整える「テクニカルSEO」が欠かせません。専門的に聞こえますが、基本的なポイントを押さえるだけでも大きな差が生まれます。
ここでは、観光サイトで特に重要な「表示速度とモバイル対応」「構造化データ」「内部リンク設計」の3つのポイントに絞って解説します。
PageSpeed Insights(ページスピードインサイト)とは?見方や改善方法について
ページ表示速度とモバイル対応の強化
旅先で情報を探すユーザーの多くは、通信環境が必ずしも良くない場所でスマートフォンを利用しています。そのため、サイトがモバイル端末で快適に表示・操作できる「モバイルフレンドリー」であることは絶対条件です。Googleもモバイルサイトを主軸に評価する「モバイルファーストインデックス」を完全移行しており、モバイル対応はSEOの基本中の基本と言えます。
具体的な改善策としては、画像のファイルサイズを圧縮・最適化する、WebPのような次世代フォーマットの画像を利用する、ブラウザキャッシュを活用して再訪問時の読み込みを速くする、不要なCSSやJavaScriptのコードを削除するといった施策が挙げられます。Googleの「PageSpeed Insights」という無料ツールで自サイトの速度を計測し、改善点を確認することから始めましょう。
構造化データによる検索結果の強調表示
「構造化データ」とは、ページに書かれている情報が「何であるか」を検索エンジンが明確に理解できるように、特定の書式(スキーマ)でマークアップするHTMLコードのことです。これを適切に設定することで、検索結果画面で通常よりもリッチな形式(リッチリザルト)で表示される可能性が高まります。
例えば、イベント情報をマークアップすれば、検索結果にイベント名、日時、場所が一覧で表示されます。Q&Aページに実装すれば、質問と回答がアコーディオン形式で表示されます。
観光業界では特に、Hotel(ホテルの星評価や価格帯)、Restaurant(レストランの評価や料理の種類)、TouristAttraction(観光名所)、Event(イベント情報)、FAQPage(よくある質問)といったスキーマが非常に有効です。これらのリッチリザルトは検索結果画面で非常に目立つため、競合サイトよりもクリックされる確率を大幅に高める効果が期待できます。
実装には専門知識が必要な場合もありますが、JSON-LDという記述形式が推奨されており、Googleの「リッチリザルトテスト」ツールで正しく実装できているかを確認できます。
内部リンクとカテゴリ設計の最適化
「内部リンク」とは、自社サイト内のページ同士を繋ぐリンクのことです。これが戦略的に設計されていると、ユーザーは関連情報へスムーズに移動できるため回遊性が高まり、サイト滞在時間が長くなります。
SEOの観点からは、検索エンジンにサイトの構造と各ページの関連性を伝え、どのページが重要であるかを示す役割も果たします。例えば、「箱根の観光モデルコース」というまとめ記事から、「箱根彫刻の森美術館の楽しみ方」「箱根の温泉旅館おすすめ5選」といった詳細記事へリンクを貼る「トピッククラスターモデル」という構造は、専門性を高めサイト全体の評価を向上させるのに有効です。
また、ユーザーがサイトのどこにいるかを示す「パンくずリスト」(例:ホーム > 関東地方 > 神奈川県 > 箱根の観光情報)を設置することも、ユーザビリティとSEOの両面で重要です。
サイト全体のトピックを分かりやすく整理したカテゴリ構造と、文脈に沿った適切な内部リンク設計は、ユーザーと検索エンジンの両方にとって分かりやすいサイト作りの基本です。
Googleビジネスプロフィールとの連携
WebサイトのSEOと車の両輪で進めるべきなのが、「Googleビジネスプロフィール(GBP)」の最適化です。これは「MEO(Map Engine Optimization)」や「ローカルSEO」とも呼ばれ、特に「地域名+業種」といった検索において絶大な効果を発揮します。
ここでは、GBPの基本的な最適化から、口コミや投稿機能の活用まで、地域での集客を強化する具体的なポイントを解説します。
ローカルSEOとは何か??MEOの違いからどのような施策があるのかまで詳しく解説
MEO・ローカルSEOで地域集客を強化する方法
「箱根 温泉」「渋谷 ランチ」のようにユーザーが地域を指定して検索した際、検索結果の上部に地図とともに表示される3枠のビジネス情報(ローカルパック)に自社情報を掲載させる施策がMEOです。このエリアに表示されるか否かで、クリック数、そして実店舗への来店数は劇的に変わります。
Googleはローカル検索の順位を決定する要因として主に「関連性」「距離」「視認性の高さ(知名度)」の3つを挙げています。「関連性」はGBPの情報がユーザーの検索語句とどれだけ一致しているか、「距離」は検索された場所からビジネス所在地までの距離、そして「視認性の高さ」はビジネスがどれだけ広く知られているか(Web上の言及数や口コミ、被リンクなども影響)を指します。
MEOは、これらの要因を理解し、GBPの情報を充実させ、オンライン上での知名度を高めていくことで、地域内での集客力を最大化する取り組みです。
観光地のGoogleマップ最適化の基本
MEOの第一歩は、GBPの情報を隅々まで正確かつ詳細に登録することです。ビジネス名、住所、電話番号(NAP情報はWebサイトと完全に一致させる)、ウェブサイト、営業時間はもちろんのこと、カテゴリ設定は特に重要です。「旅館」「ホテル」「観光名所」など、事業内容を最も的確に表すカテゴリを選択し、サブカテゴリも可能な限り設定しましょう。
さらに、近年追加された「属性」や「サービス」の項目も重要です。「Wi-Fiあり」「駐車場あり」「ペット同伴可」といった属性や、提供している具体的なサービス内容(例:「日帰り温泉プラン」「〇〇会席コース」など)を詳細に入力することで、ユーザーのより細かいニーズに応えることができます。
また、GBPに登録する写真はユーザーの第一印象を左右するため、プロが撮影した高品質な写真を多数(外観、内観、客室、料理、アメニティなど)アップロードすることが、クリック率の向上に直結します。
口コミや評価の活用による信頼構築
ユーザーが投稿した口コミ(レビュー)の数と評価(星の数)は、ローカル検索のランキングに大きな影響を与えるだけでなく、他のユーザーの意思決定を左右する最も重要な要素の一つです。ポジティブな口コミは強力な推薦状となり、ネガティブな口コミは顧客を遠ざけます。
最も重要なのは、全ての口コミに対してオーナーとして迅速かつ丁寧に返信することです。高評価の口コミには、具体的な内容に触れながら感謝を伝えましょう。一方、ネガティブな口コミに対しては、決して無視したり感情的になったりせず、まずは真摯に謝罪し、事実確認と改善策を具体的に示すことで、他のユーザーに誠実な姿勢をアピールできます。この真摯な対応は、かえって店の信頼性を高めることにも繋がります。
また、施設内での声かけや、サンキューメールにレビュー依頼のリンクを記載するなど、質の高いサービスを提供した上で、積極的に口コミ投稿を促す仕組みを作ることも大切です。
googleマイビジネスで集客をする手順と成功させるためのポイントを解説
周辺施設・宿泊地との連携による相互送客
自社の魅力だけでなく、その地域全体の魅力を高める視点を持つことも、間接的にMEOを強化します。例えば、近隣の人気の飲食店、体験施設、観光名所と連携し、お互いのGBP情報やWebサイト上で紹介し合うことは非常に有効な戦略です。
共同でスタンプラリーのようなイベントを企画し、それぞれのGBPの「投稿」機能で告知し合えば、地域全体で大きな相乗効果を生み出せます。ユーザーにとっても、一つの場所を起点として周辺の有益な情報が得られることは大きなメリットです。
地域の観光協会やDMO(観光地域づくり法人)といった公的機関と連携し、公式サイトから自社のGBPやWebサイトへリンクを貼ってもらうことも、ビジネスの「視認性の高さ(知名度)」を向上させる上で極めて効果的です。地域一体となって魅力を発信することが、巡り巡って自社への集客に繋がるのです。
ローカル検索キーワードと投稿活用のポイント
GBPに標準で備わっている「投稿」機能は、無料で使える強力な宣伝ツールです。これは、最新情報やイベント、特典などを発信できる簡易的なブログのような機能で、上手に活用することでユーザーの関心を強く引くことができます。
投稿を作成する際は、必ず魅力的な写真や動画を添付し、「〇〇(地域名) 桜 見頃」「週末限定 日帰りプラン」のように、ユーザーが検索しそうなローカルキーワードを自然な形で盛り込みましょう。
投稿の種類には「最新情報」「イベント」「クーポン」などがあり、目的に応じて使い分けることが重要です。例えば、イベント投稿では期間を設定でき、クーポン投稿では割引コードなどを表示できます。
投稿は一定期間で表示が古くなるため、週に1回など定期的に新しい情報を発信し続けることが、GBPをアクティブに保ち、Googleからの評価を高めるコツです。
SNS・外部施策と組み合わせたSEO戦略
SEOは、自社サイト内やGBPの最適化だけで完結するものではありません。SNSや他のWebサイトといった外部のプラットフォームと連携し、オンライン上での評判を高めることで、その効果を飛躍的に高めることができます。
ここでは、SNSでのコンテンツ拡散、外部リンクの獲得、インフルエンサーやユーザー投稿(UGC)の活用といった、外部施策と連携する具体的なSEO戦略を解説します。
SNS連携によるコンテンツの拡散効果
Instagram、X(旧Twitter)、Facebook、TikTokといったSNSは、作成したSEOコンテンツをより多くの人に届けるための強力な拡散装置です。
例えば、絶景スポットを紹介する記事を公開したら、その中で最も魅力的な写真をInstagramに投稿し、プロフィール欄のリンクから記事へ誘導します。季節のイベント情報をXでリアルタイムに発信し、公式サイトのプランページへ繋げることも有効です。
SNSで「いいね」や「シェア」が多く集まる(エンゲージメントが高い)と、直接的なSEO効果は無いとされていますが、コンテンツが多くの人の目に触れることで、他のブロガーやメディアが記事で言及してくれる機会が増えます。
これが「サイテーション(言及)」や「ナチュラルリンク(自然な被リンク)」の獲得に繋がり、間接的に検索エンジンからの評価を高めることに貢献します。各SNSのユーザー層や特性を理解し、コンテンツに合わせた最適な発信方法を模索しましょう。
外部リンク獲得を意識した情報発信
他の質の高いWebサイトから自社サイトへ向けられたリンク(外部リンク、被リンク)は、Googleがサイトの権威性や信頼性を評価する上で最も重要な指標の一つです。多くの信頼できるサイトから推薦されているサイトは、有益なサイトであると判断され、検索順位が向上しやすくなります。
質の高い被リンクを獲得するためには、リンクを貼りたいと思わせるような価値のある情報発信が不可欠です。例えば、地域独自の文化や歴史に関する深い考察記事、観光客動向に関する独自の調査データをまとめたレポート、魅力的な切り口のプレスリリースなどを発信し、地域のニュースサイトや観光専門メディア、公的機関(自治体や観光協会)に取り上げてもらうことを目指します。
また、取引先や提携先のウェブサイトに自社を紹介してもらうよう依頼することも有効な手段です。ただし、金銭を支払ってリンクを購入するなどのGoogleのガイドラインに違反する行為は、ペナルティのリスクがあるため絶対に避けましょう。
インフルエンサーとの連携で認知度アップ
特定の地域やジャンル(グルメ、温泉、アウトドアなど)において強い影響力を持つインフルエンサーとの連携は、短期間で認知度を向上させ、ターゲット層に直接アプローチできる効果的な施策です。
重要なのは、単にフォロワー数が多いだけでなく、自社のブランドイメージやターゲット顧客と親和性が高く、フォロワーとのエンゲージメント(いいね、コメントなど)が活発なインフルエンサーを選定することです。
彼らに実際に施設やサービスを体験してもらい、その魅力を自身の言葉でSNSやブログで発信してもらうことで、広告にはない「リアルな口コミ」としてユーザーに受け入れられます。
施策の効果を測定するため、インフルエンサー経由の予約専用の割引コードを発行したり、パラメータ付きのURLを提供したりして、どれくらいのアクセスやコンバージョンに繋がったかを追跡できるようにしておくと、次回の施策の改善に繋がります。
UGC(ユーザー投稿)を活用した信頼性向上
UGC(User Generated Content)とは、インフルエンサーではなく、一般のユーザーによって作成されたコンテンツのことです。Instagramの写真投稿や旅行口コミサイトのレビューなどが代表例です。
企業からの発信情報よりも、第三者である一般ユーザーからのリアルな声は「社会的証明(ソーシャルプルーフ)」として働き、他のユーザーの意思決定に極めて大きな影響を与えます。
UGCを増やすためには、例えば「#〇〇旅館の思い出」といった独自のハッシュタグを作成し、投稿を促すフォトコンテストを開催したり、施設内に写真映えするスポット(フォトブース)を設置したりする施策が有効です。
集まったUGCは、事前にユーザーから許諾を得た上で、公式サイトやSNSの公式アカウントで紹介することで、さらなるUGCの創出を促す好循環が生まれます。こうしたユーザーとの双方向のコミュニケーションは、強力なファンコミュニティを形成し、長期的なブランドロイヤルティの向上に貢献します。
SEO施策の効果測定と改善方法
SEOは、施策を実施して終わりではありません。その効果をデータに基づいて客観的に測定し、継続的に改善していく「PDCAサイクル」を回すことが、持続的な成果を生み出すために不可欠です。
ここでは、効果測定に必須のツール活用、目標となるKPIの設定、そして具体的な改善アクションであるコンテンツリライトについて解説します。
GoogleアナリティクスとSearch Consoleの活用
SEOの効果測定には、Googleが無料で提供する「Google Search Console」と「Google Analytics (GA4)」の2つのツールが必須です。
まず、Google Search Consoleは、サイトがGoogle検索でどのように表示されているかを知るためのツールです。どのキーワード(クエリ)で表示され、何回クリックされたか、平均掲載順位はどうだったかなどを確認できます。また、Googleがサイトを正しく認識できているか(インデックス状況)や、モバイル対応の問題点など、技術的な健全性をチェックする上でも欠かせません。
一方、Google Analytics (GA4)は、サイトに訪れたユーザーが「その後どう行動したか」を分析するツールです。検索エンジンから来たユーザーがどのページを閲覧し、どれくらいの時間滞在し、最終的に予約や問い合わせ(コンバージョン)に至ったかを詳細に追跡できます。
この2つのツールを連携させることで、「どんなキーワードで来たユーザーが、最もコンバージョンに繋がりやすいか」といった、より深い分析が可能になります。
サーチコンソール活用ガイド|SEO改善と検索順位アップのための必須ツール
CV数・流入数などKPIの設定と可視化
効果測定を行うためには、施策を始める前に「何を達成目標とするか」という具体的な指標、すなわちKPI(重要業績評価指標)を設定することが極めて重要です。
最終的なゴール(KGI:重要目標達成指標)が「自社サイト経由の宿泊予約数を月間50件にする」だとすれば、それを達成するための中間指標としてKPIを設定します。
例えば、「主要キーワード(例:地域名 旅館)での検索順位3位以内」「自然検索からの月間セッション数10,000」「宿泊プランページの閲覧数から予約完了画面への遷移率5%」といった具合です。
このように目標を数値化し、KPIツリーとして構造化することで、チーム内での目標共有が容易になり、施策の進捗状況を客観的に評価できます。
これらのKPIは、Looker Studio (旧Googleデータポータル) などのBIツールを使ってダッシュボードとして可視化し、いつでも確認できるようにしておくことが、迅速な意思決定と改善アクションに繋がります。
定期的なコンテンツリライトの実施
一度公開した記事は、情報の陳腐化や競合の出現によって、時間とともに検索順位が下落していくことがあります。そのため、既存のコンテンツを定期的に見直し、最新の情報に更新したり、内容を拡充したりする「リライト」は非常に重要な運用業務です。
リライトの対象となる記事は、Search Consoleのデータから見つけることができます。例えば、「表示回数は多いのにクリック率(CTR)が低い記事」は、タイトルやディスクリプションが魅力的でない可能性があります。「掲載順位が11位~20位あたりで停滞している記事」は、もう少しで1ページ目に表示されるポテンシャルを秘めており、内容を強化することで順位上昇が期待できます。
リライトを行う際は、再度キーワード調査を行い、ユーザーの新たなニーズや検索意図の変化を把握した上で、競合の上位サイトが必要としている情報要素を追加したり、独自の視点や最新情報を加えたりして、コンテンツの質を高めていくことが求められます。
まとめ
本記事では、観光業界で集客を強化するSEOの実践ノウハウを解説しました。
ユーザーの検索行動を捉えるキーワード戦略から、体験価値を伝えるコンテンツ作成、MEO連携、データに基づく効果測定まで、成果に繋がる要点は多岐にわたります。
SEOは継続的な改善が必要な息の長い施策ですが、正しく取り組むことで、広告費に依存しない安定した集客と、施設のブランド価値向上という大きな果実を得ることができます。
もし社内でのSEOサイト運用に限界を感じている場合は、SEO対策のプロに相談してみましょう。楽々Editでは、無料相談会を実施しています。ぜひ、お気軽にお問合せください。

合同会社楽々Edit 代表 山本 伸弥(やまもと しんや)
新卒でSEOコンサルティング会社に入社し、SEOコンサルタントとして戦略立案から営業、コンテンツ制作まで幅広く従事した後に、合同会社楽々Editを創業し代表取締役に就任。 中小企業から東証プライム企業、ベストベンチャー100まで累計300社以上のSEO改善実績を持つ。 国内大手SEOマーケティング会社10社とデジタルマーケティングカンファレンスも主催している。
\成果が出ていない原因をまとめたレポートをご提供/
\ SEO無料相談会はこちら/
SEO対策の無料相談会を開催中です。転職やクリニック業界などジャンルを横断して競合性の高いキーワードで実績のある弊社にぜひご相談ください。

