歯医者が見直すべき集客方法とは?新しい患者を増やすための施策を徹底解説!
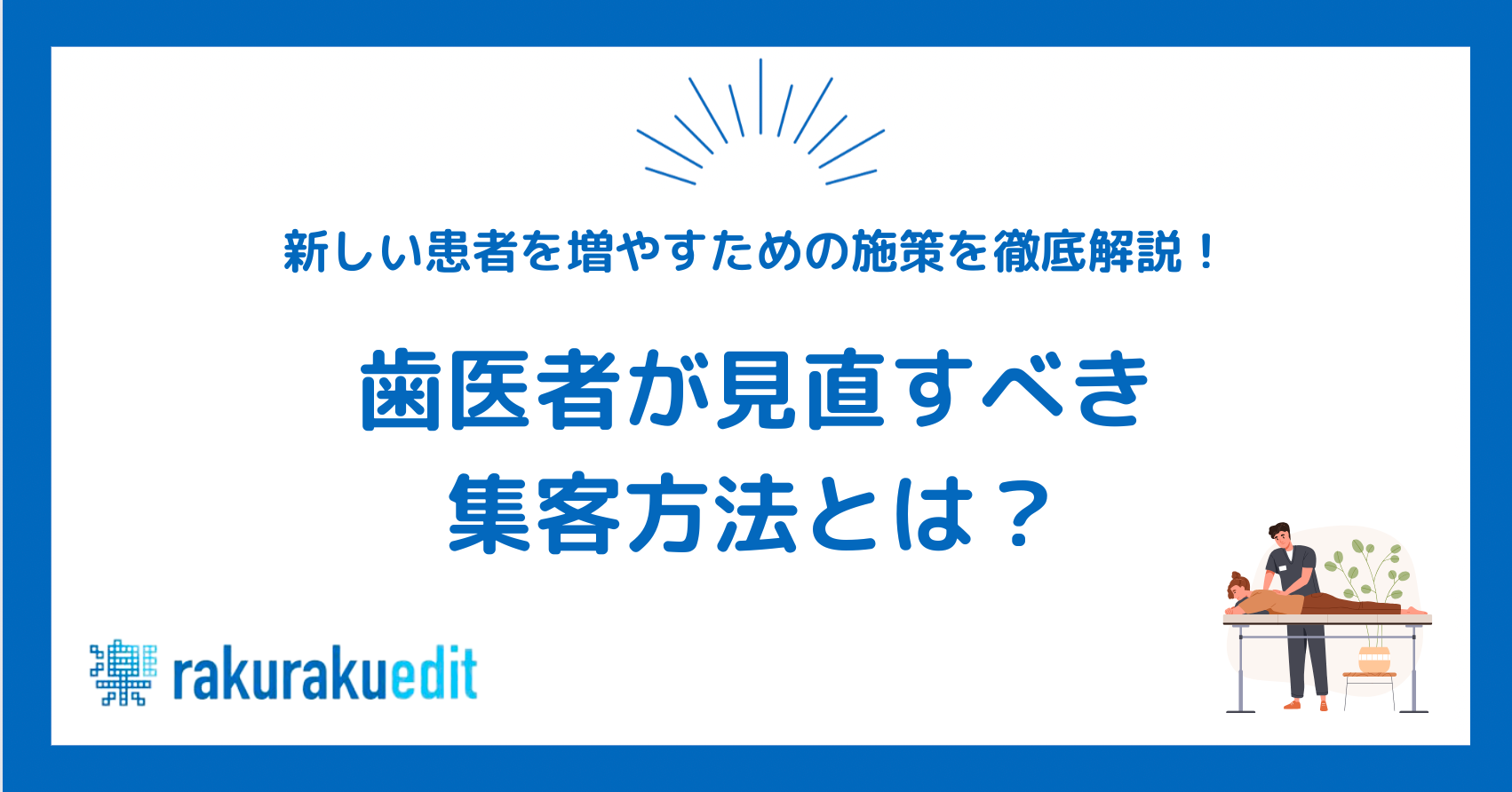
「最近、新患の予約が減ってきた……」「Webサイトを立ち上げたのにイマイチ集客につながらない……」そんな悩みを抱える歯医者は少なくありません。患者が来ない原因は、間違った集客方法を行っている可能性があります。
そこで本記事では、7つの効果的集客方法や、集客を成功させる4つのポイントを徹底解説します。安定した集客を行い、予約でいっぱいになるような歯医者を目指しましょう。
歯医者の集客がうまくいかない原因を解説

歯医者の数が増え続ける中、どれだけ診療技術が優れていても集客でつまずいてしまったら元も子もありません。歯医者の集客がうまくいかない原因はいくつかあります。ここでは、歯医者が陥りがちな集客の失敗要因を3つに分けて詳しく解説していきます。
ポータルサイトに頼りきり
多くの歯医者が、集客の大部分を大手のポータルサイトに依存しています。ポータルサイトは初期集客には効果的ですが、競合も多数掲載されているため差別化が難しく、費用対効果が下がる傾向があります。さらに、リピーターや医院のファン化につながりにくいのが弱点です。
例えば、ポータルサイト経由で月10人の新患が来ていた医院が、サイト内の順位が下がった途端、予約が激減してしまいました。自院のホームページやSNSを活用していなかったため、他の流入経路がなく一気に来院数が落ちたのです。
ポータルサイトは「入り口の一つ」として活用しつつ、自院のホームページ・Googleビジネスプロフィール・SNSなど自前の集客基盤を整えることが安定した集患には不可欠です。
Webサイトが古いまま
昨今、多くの患者は歯医者を探す際に、まずWebサイトをチェックしてから来院するかどうかを判断しています。Webサイトが古いままだと情報の信頼性が低く感じられたり、「本当にやってるのかな?」「設備が古いのでは?」などの不安につながったり、来院をためらう原因になりかねません。また、スマートフォン非対応のページは閲覧しづらく、途中で離脱されやすくなる要因の一つです。
例えば、2008年に作ったままのWebサイトを使っていた歯医者では、診療時間や対応内容の誤情報が原因でクレームにつながったり、見た目の古さから「通うのが不安」などの声が患者から出たりする事例もあります。
患者の信頼を得るためには情報の鮮度を保ち、定期的に見直す姿勢が欠かせません。治療内容や診療時間、価格、導入している設備などに変更があった場合は、すぐに最新情報をWebサイトに反映させましょう。
Webサイトは、言うならば「医院の顔」です。スマートフォン対応・最新情報の反映・安心感のあるデザインに整えることで、信頼と集客力を大きく高められます。
院内の雰囲気が伝わっていない
多くの患者さんは、治療技術だけでなく「通いやすさ」や「安心感」も重視して歯医者を選んでいます。院内の雰囲気がWebサイトやSNSで伝わらないと、「怖そう」「清潔感がなさそう」「子ども連れでも大丈夫かな?」などが不安を払拭できず、来院の決め手になりません。写真や動画で院内の空気感が分かると、初診のハードルが下がります。
例えば、とある小児歯科では、Webサイトに診療案内やアクセス情報は載っていたものの、院内の写真やスタッフの雰囲気が一切伝わらない構成になっていました。
実際にその医院の近くに住む30代の母親が口コミサイトに「初めての子どもを連れて行くには情報が少なくて不安。キッズスペースや先生の雰囲気が分かる写真があれば安心できた」と投稿。結果的にその患者さんは、Instagramで院内の様子やスタッフ紹介を積極的に発信していた少し離れた場所にある別の医院を選んだという経緯があります。
院内の写真・動画・スタッフ紹介などで、安心感や親しみやすさを視覚的に伝えることが集客アップには欠かせません。患者が「ここなら通えそう」と思える情報発信を心がけましょう。
歯医者の集客方法7選
患者が集客できない原因の一つに、集客施策が偏っている場合があります。集客にはさまざまな方法がありますが、一つの施策だけに頼っていると集客率もグンと減るでしょう。
そこで大切なのが、複数の集客施策を組み合わせて活用する戦略です。オンラインとオフラインの両軸で動き、各施策の特性を理解したうえで使い分けることで集客向上が期待できます。
ここでは、歯医者の代表的な集客方法を7つ解説します。それぞれの狙いや実践ポイントを見ていきましょう。
SEO対策
多くの患者さんは「地域名+歯医者」などのキーワードで検索して歯医者を探しています。検索結果の上位に表示される医院ほど、クリック率・来院率が高くなります。
SEO対策を行うことで検索エンジンでの表示順位が上がり、自院のWebサイトへのアクセスが増加するでしょう。アクセスが増えることで認知度が高まり、新患の獲得につながる可能性が広がります。
例えば、「〇〇市 インプラント」で地域上位表示されるようにSEO対策を行った歯医者では、毎月10件以上の問い合わせがコンスタントに入るようになり、広告費を削減しながら新患数が安定したという実績があります。
SEO対策は一時的なテクニックではなく、「患者が探している情報を分かりやすく届ける」ことが基本です。地域名・診療内容・よくある質問など、患者視点のコンテンツを充実させることが検索上位への近道です。
SEO対策とは?やり方や方法・無料の検索上位表示ツールも解説
MEO対策
患者さんの多くは「地域名+歯医者」などで検索した際に、Googleマップに表示された上位の医院を見て選んでいます。MEO対策を行うことでGoogleマップ上での表示順位が上がり、地域の検索ユーザーに直接リーチできます。Webサイトよりも視覚的に分かりやすく、行動(電話・ルート検索・予約)につながりやすいのが特長です。
例えば、ある地方の歯医者では、Googleビジネスプロフィールに医院の外観・内観写真、診療内容、スタッフ紹介、定期的な投稿、口コミ返信を丁寧に行ったところ、Googleマップ経由の来院数が月平均で1.5倍に増加した実例があります。
MEOは「地域の患者さんに見つけてもらうための最前線」です。写真・情報の充実、口コミの管理、定期的な投稿を通じて、信頼感と認知度を高めることが集客アップのポイントとなります。
SNS運用
最近ではInstagramやLINEなどのSNSを見て、「この歯医者さんに行ってみたい」と感じる患者が増えています。特に若年層やファミリー層はSNSで情報収集する傾向が強いです。SNSは医院の雰囲気や人柄、日常の取り組みを親しみやすく伝えられるツールです。広告的ではない自然な発信が信頼感や安心感につながり、医院への関心を高めます。
例えば、ある小児歯科ではInstagramで「スタッフの笑顔」「キッズスペース紹介」「お子さん向けイベントの様子」などを投稿したところフォロワーが500人を超え、「SNSを見て来ました」といった具合で新患が毎月安定的に増加するようになりました。
SNSは、患者との接点を増やす窓口として継続的な集客に効果的です。一方通行の発信ではなく、コメントやDMでの交流も取り入れることで、来院前から信頼関係を築けます。新患だけでなく、既存顧客に対しても効果的な集客方法の一つです。
Web広告
Google広告やInstagram広告などのWeb広告は、地域や年齢、興味関心などを絞って「今まさに歯医者を探している人」にピンポイントでアプローチできます。Web広告はターゲットに合わせて表示内容を最適化できるため、新患のニーズに合った訴求が可能です。また、効果をデータで確認・改善できるため費用対効果が高く、短期間で結果が出やすいことも特徴として挙げられます。
例えば、ある審美歯科では「ホワイトニング+地域名」でGoogle広告を運用したところ、1ヶ月で30件以上の問い合わせがあり、そのうち半数以上が新患として来院した実績があります。従来のチラシよりも高い反応率を得られました。
Web広告は、「今すぐ患者になり得る人」にリーチできる即効性のある集客手段です。ホームページやSNSと組み合わせて使うことで相乗効果が生まれ、安定した新患獲得につながります。
チラシ・ポスティング
WebやSNSが主流になった今でも、地域密着型の歯医者ではポスティングによる集客が一定の効果を発揮しています。ポスティングはインターネットを使わない層や、近隣に住む潜在患者に直接アプローチできる手段です。とくに高齢者やファミリー層にとっては、紙の情報が身近で安心感につながるケースが多くあります。
例えば、ある住宅地にある歯医者では、「予防歯科・無料相談会」の案内をポスティングしたところ、配布から2週間で10件以上の問い合わせと予約が発生しました。Webでは届かない層からの反応が中心で、地域での認知度アップにもつながりました。
ポスティングは「地域住民への直接的なアプローチ」として、特に開院初期やキャンペーン時に効果的です。デザインや内容、配布エリアを工夫することで、Web施策との相乗効果も期待できます。
看板や街頭広告
歯医者の近くに住む人や通勤・通学路として通る人たちは、日常的に目にする看板や街頭広告から無意識に医院の存在を認識しています。看板や街頭広告は「ここに歯医者がある」という視覚的な認知を高め、来院のきっかけをつくるツールとなるでしょう。特に、通行量の多い道路や交差点付近に設置すれば、地域での認知度アップにも期待できます。
例えば、ある郊外の歯医者では、国道沿いに「〇〇歯科 右折500m」の案内看板を設置したところ、「いつも通っていて気になっていた」という理由での来院が増加しました。実際に新患アンケートで「看板を見て来院した」などの回答が3割を占めた実績があります。
看板・街頭広告は「認知のきっかけをつくるリアルなメディア」として、Web集客では届かない層へのアプローチに効果的です。医院名・場所・診療内容を明確にし、地域との接点を増やしましょう。
口コミ・紹介
患者が歯医者を選ぶ際、Googleの口コミや知人からの紹介が決め手になるケースは非常に多く、信頼性の高い情報源として重視されています。歯科治療は「痛そう・怖そう」という不安を感じやすい分野だからこそ、実際に通っている人の口コミや紹介が、安心と信頼を与える最大の材料となります。広告よりも信ぴょう性が高く、来院意欲が強まる傾向にあると覚えておきましょう。
例えば、ある地域密着型歯医者で「紹介カードを渡したら初診料が割引になる」制度を取り入れたところ、紹介による新患数が月平均10から15件に増加したそうです。患者同士の信頼関係がそのまま医院への信頼へとつながりました。
口コミ・紹介は、信頼で集める最強の集客手段です。質の高い診療・丁寧な対応を徹底することに加え、口コミ投稿をお願いする仕組みや紹介しやすい工夫を取り入れることで、自然な形で集患につなげられます。
歯医者の集客を成功させるための4つのポイント
歯医者が集客を成功させるポイントは、以下4つの施策を同時に実行することです。
- 複数の施策を組み合わせる
- 来院までの導線を見直す
- 継続的な改善・検証
- 自費医療の治療も増やす
ここでは、上記4つの施策を行い、継続的に安定した集客へとつなげるポイントを解説します。
複数の施策を組み合わせる
現在の患者さんは一つの情報だけで歯医者を選ぶのではなく、Web検索・地図・SNS・口コミなど複数の情報を組み合わせて来院を判断します。
SEOやMEOで「見つけてもらう」、SNSで「雰囲気を伝える」、看板やポスティングで「認知を広げる」、口コミや紹介で「信頼を得る」など、各施策の役割は異なるため、それぞれの施策を掛け合わせることで患者の意思決定を多角的にサポートできるようになります。つまり、あらゆる接点から「選ばれる確率」が高まる可能性大です。
例えば、ある都市部の歯医者では、WebサイトをSEO対策しつつ、Googleビジネスプロフィールも最適化し、SNSで院内の雰囲気を発信しました。さらに、地域にポスティングを行い、紹介制度も実施した結果、半年で新患数が約2倍に増加して「色んなところで目にして気になった」などの声が増えた事例があります。
単発の施策よりも、複数の集客チャネルを連動させることで「認知 → 関心 → 信頼 → 来院」までの導線が強化され、安定した集客につながります。患者との接点の総量を増やすことが現代の集患成功のポイントです。
Webマーケティングの代行サービスをうまく活用するには?選び方やメリットを解説!
来院までの導線を見直す
多くの患者は歯医者を見つけてから実際に予約・来院するまでに、Webサイト・地図・口コミ・電話や予約フォームなど、複数のステップをたどります。
導線が分かりづらかったり、途中で不安を感じたりすると「行こうと思ったけどやめた」という離脱が発生します。特にスマートフォンの利用が主流の今、予約までの流れがスムーズかつ安心できる構成であることが大切です。
例えば、ある歯医者ではWebサイトの構成を「診療内容 → 院内の雰囲気 → よくある質問 → 予約フォーム」というよう初めての方が迷わずたどれる流れに改善したところ、Web経由の予約率が2倍に増加しました。
来院までの導線を見直すには、「患者目線で一連の流れを体験し、どこで不安や手間が生まれているか」を確認することがポイントです。見つけてもらう施策(SEO・MEO)だけでなく、「来たくなる・予約したくなる仕組み」も整えましょう。
継続的な改善・検証
集客施策は一度実施したら終わりではなく、患者のニーズや検索傾向、競合状況は常に変化しています。一度うまくいった方法でも、時間の経過とともに効果が薄れたり、競合に追い越されたりするリスクがあるため、定期的に結果を検証して改善を重ねることが安定した集客につながります。
例えば、ある歯医者ではGoogle広告の効果が伸び悩んだ際、キーワードや広告文を見直して再設定したところ、1クリックあたりの費用が下がり、予約数も2倍に増加した実例があります。継続的に数値を追いながらPDCAを回すことで、効率よく集客できるようになりました。
集客は「一度やって終わり」ではなく、「育てていくもの」です。アクセス解析や広告レポート、口コミの内容などを定期的に見直し、小さな改善を積み重ねることで長期的な集客力が高まります。
自費医療の治療も増やす
近年、多くの歯医者が自費診療(インプラント・矯正・ホワイトニングなど)に注力し始めており、保険診療だけに依存しない経営スタイルが主流になりつつあります。自費診療は保険診療に比べて単価が高く、治療の質や選択肢も広がるため、医院の収益性向上に直結します。
また、自由診療を通じて「美」「予防」「快適さ」など患者の多様なニーズに応えやすくなり、他院との差別化にも効果的です。
例えば、ある歯医者ではWebサイトやSNSを通じてホワイトニングやセラミック治療の情報を発信し、自費診療の相談窓口を強化しました。その結果、毎月の自費割合が全体の15%から30%に増加し、経営の安定化に成功しました。
自費診療を増やすことは医院の経営基盤を強化し、患者の満足度を高めるためにも大切な戦略です。そのためには、集客導線の中で「自費診療の魅力を正しく伝える」情報設計が欠かせません。
歯医者の集客施策の3つの注意点
集客に力を入れる歯医者が増える一方で、やみくもに施策を始めてもうまくいかないケースも少なくありません。効果を最大化するためには、「すぐに結果が出るとは限らないこと」「院内リソースを把握してから実行に移すこと」「自院の強みを適切な表現で発信すること」などの基本的だけど見落とされがちなポイントを意識することが欠かせません。
ここでは、集客の失敗を防ぐために押さえておきたい3つの注意点を解説します。
すぐに効果が出るとは限らない
SEO対策や口コミ施策、SNS運用など、多くの集客手法は一定の成果が出るまでに数週間〜数ヵ月の時間がかかることが一般的です。歯医者の集客は「今すぐ治療が必要な人」だけでなく、「何かあったら行こう」と考えている潜在層へのアプローチも必要不可欠になります。患者の意思決定に時間がかかるケースが多いため、短期的な反応だけで成果を判断するのは危険です。
例えば、ある歯医者がWebサイトをリニューアルしてSEO対策を強化したものの、最初の1ヶ月はアクセスが伸び悩みました。しかし、3ヵ月目以降から検索順位が上昇し、徐々に予約が増加したのです。6ヵ月後には新患が月20%増加という成果につながりました。
集客施策は「育てていくもの」と考え、短期的な効果に一喜一憂せず、継続的な改善と検証を通じて中長期で成果を出す視点が大切です。
自院で集客施策を行う場合はリソースを確認してから実行する
Web更新やSNS運用、広告管理などの集客施策は手間と時間がかかる業務であり、日々の診療業務と並行して取り組むには負担が大きい場合があります。
スタッフのスキルや時間、ツールの有無などを確認せずに施策を始めてしまうと、中途半端な運用になり、かえって信頼を損ねたり、成果につながらなかったりするリスクがあるため、事前に自院のリソースを見極めておくことが不可欠です。
例えば、ある歯医者でInstagramでの集客を試みたものの、投稿が不定期になり、内容も一貫性がなくフォロワーが増えなかったという失敗を犯しました。その後、院内で運用できる範囲を見直し、月1回の撮影と週1回の投稿体制に変更したことで安定した成果が出るようになりました。
自院で集客を行う際は「誰が・どこまで・どの頻度で」対応できるのかを明確にした上で、現実的な施策を選ぶことが成功のポイントです。無理のない体制づくりが、継続的な集患へとつながります。
適切な表現で自院の特徴を発信する
多くの患者は、歯医者を選ぶ際に「どんな医院か?」「自分に合っているか?」をホームページやSNSなどで確認してから来院を決めています。特徴が曖昧だったり、専門用語ばかりで伝わりづらかったりすると、患者は「よく分からないから別の医院にしよう」と離脱してしまう可能性が高くなります。伝え方ひとつで集客の成果が大きく左右されるのです。
例えば、ある歯医者では「丁寧な説明」とだけ記載していた表現を、「治療前に写真を用いて視覚的にご説明し、ご納得いただいた上で治療を進めます」と具体的な内容に変更しました。その結果、安心感が伝わりやすくなり、初診の問い合わせが増加しました。
自院の魅力や強みは、誰に・どう伝えるかが大切です。患者目線で分かりやすく、親しみやすい表現にすることで、信頼感が高まり、自然と選ばれる医院へと近づきます。
商品の魅力を伝える文章とは?コツや魅力的な文章を書くポイントを解説!
【番外編】既存患者の来院率を高める5つの方法
一度来院した患者に継続して通ってもらうことは、歯医者の安定経営にとって非常に大切です。集客と聞くと「新患を増やすこと」に意識が向きがちですが、「既存患者の再来院率を上げること」も経営を安定させるには欠かせない視点になります。
ここでは、既存患者との関係性を維持・強化し、自然な流れで再来院につなげるための方法を5つ紹介します。
施術終了後に次回の予約を入れる
施術後に次回の予約をその場で取ることは多くの歯医者で実施されている方法で、患者の来院率向上や予約の確保に効果的とされています。
患者は治療の際に痛みや不安が伴うことが多く、次回の治療を事前に予約することで不安を感じずにスムーズに治療を継続できるため、通院を続けやすくなるからです。また、次回の予約をその場で取ることで、患者にとって「忘れずに通院できる」「計画的に治療を進められる」という安心感を提供できます。
例えば、ある歯科医院では治療後の患者に「次回の予約を取っておきませんか?」と声をかけたところ、約7割の患者がその場で次回の予約を入れるようになり、来院率が大幅に向上しました。この方法を取り入れた結果、再診率が20%向上したそうです。
次回予約をその場で入れることで患者にとって通院ハードルが下がり、歯医者側も安定した患者数を確保できるため、効果的な集客手段となります。このアプローチを習慣化することで患者との関係も強化され、長期的な通院につながります。
施術後に定期健診の大切さを伝える
多くの歯医者では、治療後に定期的な健診の大切さを伝えることが再来院を促す効果的な方法とされています。歯科治療はすべての施術が終わったら通院も終わりと認識する患者も多いですが、実際は虫歯や歯周病の早期発見・予防につなげるために定期健診は欠かせません。施術後に定期健診を提案することで、患者が再訪を忘れず、継続的な治療が可能になります。
例えば、ある歯医者では治療後にスタッフが「次回の定期健診を受けることで、再発を防げますし、健康を守るためにとても大切ですよ」と伝え、その場で定期健診の予約を取るシステムを導入しました。その結果、定期健診の予約率が40%から70%に増加し、患者の継続受診が促進されました。
施術後に定期健診の大切さをしっかり伝えることで、患者にとって「予防の大切さ」を意識させることが可能です。その結果、既存顧客の再来院率が高まり、集客の悩みが一つ減るでしょう。
定期健診の案内を送る
定期健診の案内を患者に送ることは、再来院を促す効果的な方法として、多くの歯科医院で実施されています。特に、案内を送るタイミングや内容がポイントです。
患者は忙しい中で歯科医院の定期健診を忘れがちです。案内を送ることで、患者にとっての「予防の大切さ」を再認識させ、次回の来院を促進できます。定期的な案内を通じて、患者に継続的な通院を促すことが可能になります。
例えば、ある歯医者では治療が終わった患者に対して、3ヵ月ごとに定期健診の案内を郵送し、その案内に加えて「次回の予約をお忘れなく」というリマインダーを記載しました。これにより、定期健診の予約率が30%から50%に増加し、安定した集客が実現しました。
定期健診の案内を患者に送ることで次回の来院を忘れることなく継続的な患者の通院を確保することができるため、安定した集客につながります。また、案内文に特典や割引を加えることで、さらに患者の関心を引きやすくなります。
患者の悩みや不安を聞き入れ施術をする
多くの患者は、治療に対する痛みや不安、過去の嫌な経験などを抱えながら来院しています。その気持ちにしっかり耳を傾ける歯医者は、信頼を得やすくなります。患者の声を丁寧に聞くことで、安心感や信頼感が生まれ、「またこの歯医者にお願いしたい」と思われやすくなるからです。
例えば、ある歯医者では初診時に5分ほど患者の悩みをヒアリングする時間を設けたところ、「話をしっかり聞いてくれて安心した」と口コミ評価が上昇しました。その結果、既存患者だけでなく、新患の来院も増えたという成果が出ました。
患者の不安や悩みに寄り添う姿勢が歯医者の信頼を高め、リピートや紹介につながる大切な集客要素となります。
自費医療の患者を獲得して通院率を上げる
保険診療に比べて自費診療は、治療の自由度や質の高い選択肢を提供できる反面、費用面で患者が慎重になるケースが多くあります。そのため、患者に対して「自費診療のメリット」や「長期的な価値」を丁寧に説明し、納得してもらうことが大切です。さらに、信頼関係を築いた上での提案は、継続的な通院やリピートにもつながりやすくなります。
例えば、ある歯医者では自費診療を希望しそうな患者に対し、症状や希望に合わせて複数のプランを提示し、治療の流れと費用を丁寧に説明しました。加えて、治療後のアフターケアにも力を入れた結果、通院の継続率が高まり、紹介による自費患者も増加しました。
自費診療の集客は「丁寧な説明」「信頼の構築」「明確な価値の提示」がポイントです。一度納得してもらえれば、通院の習慣化・高単価治療・紹介の流れが生まれ、医院の安定経営にもつながります。
まとめ|患者が来ない歯医者から脱却しよう
歯科医院の集客は、継続的な情報発信と導線設計の見直しで改善できます。SEOやMEO、SNS運用、口コミ・紹介など複数の施策を組み合わせれば、着実に来院につながるでしょう。しかし、「何から始めれば良いか分からない」とお困りの方も多いかと思います。
自院でSEOやMEO、SNS運用などを行うことが難しい場合は「楽々Edit」にお任せください。戦略立案から実行まで一貫してサポートし、成果につながる集客対策を実現します。お気軽にご相談ください。

合同会社楽々Edit 代表 山本 伸弥(やまもと しんや)
新卒でSEOコンサルティング会社に入社し、SEOコンサルタントとして戦略立案から営業、コンテンツ制作まで幅広く従事した後に、合同会社楽々Editを創業し代表取締役に就任。 中小企業から東証プライム企業、ベストベンチャー100まで累計300社以上のSEO改善実績を持つ。 国内大手SEOマーケティング会社10社とデジタルマーケティングカンファレンスも主催している。
\成果が出ていない原因をまとめたレポートをご提供/
\ SEO無料相談会はこちら/
SEO対策の無料相談会を開催中です。転職やクリニック業界などジャンルを横断して競合性の高いキーワードで実績のある弊社にぜひご相談ください。

