クリニックの集客方法を徹底解説!初心者にもわかる成功のコツと具体策
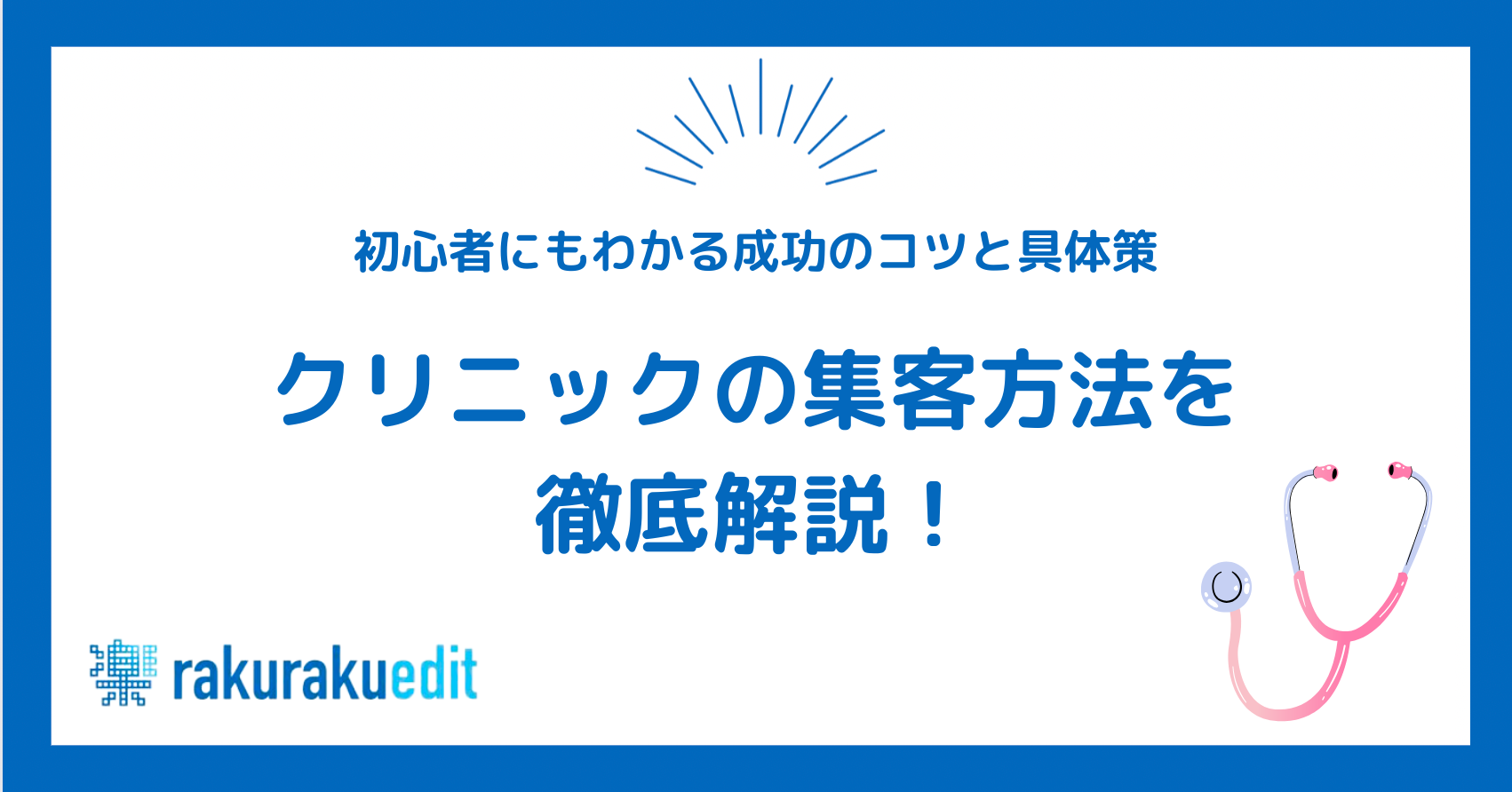
クリニックの経営において「集客」は避けて通れない問題です。いくら診療の質が高くても、患者さんに知ってもらえなければ、地域に根ざした医療は実現できません。
近年は、少子高齢化や競合クリニックの増加により、ただ待っているだけでは患者数が伸びにくい状況です。
そこで本記事では、集客に悩むクリニック経営者やスタッフの方に向けて「新規患者の獲得」と「リピーターの定着」それぞれに効果的な集客方法をわかりやすく解説していきます。
クリニック・病院の集客について知っておくべき基本知識
まずはクリニックや病院の集客について、基本的な考え方をおさえておく必要があります。特に知っておきたいのは、「新規患者」と「リピーター」では、求められるアプローチがちがうという点です。
ここではクリニックの集客について、知っておくべき基本知識を紹介していきます。
クリニック・病院における集客の重要性
クリニックや病院を安定して運営するためには、質の高い医療サービスを提供するだけでなく、患者さんに来院してもらう工夫も欠かせません。特に、地域の中で選ばれる存在になるためには、積極的な接客を行う必要があります。
最近では、インターネットで医療機関の情報を事前に調べる人が多く、ホームページやSNSなどでの情報発信が非常に重要になっています。また、診療科目や立地によってターゲット層は異なり、それぞれに合ったアプローチが求められます。
集客がうまくいけば新規患者が増えるだけでなく、リピーターの定着にもつながり、経営の安定化やスタッフの意欲向上にもつながるでしょう。だからこそ、クリニックにとって集客は「必要不可欠な取り組み」といえるのです。
「新規患者獲得」と「リピーター獲得」の違い
クリニックの集客では「新規患者」と「リピーター」それぞれに対して、異なるアプローチが求められます。
新規患者の獲得には、まず認知を広げることが重要です。チラシやWeb広告・SNS・ポータルサイトなどを活用して、自院の存在や特徴を地域に発信し、来院のきっかけをつくる必要があります。一方、リピーターの獲得は、信頼関係の構築が必要になります。
丁寧な診療、予約の取りやすさ、再診の案内、LINEやメルマガによるフォローなどが効果的です。初診後に継続して通ってもらえるかどうかは、院内の雰囲気や対応、情報提供の工夫によって左右されます。このように、集客は一度きりではなく、患者さんとの長い関係を築いていく視点を持つ必要があります。
クリニックの集客がうまくいかない主な原因
「集客のためにいろいろ取り組んでいるのに、思ったような成果が出ない」と感じているクリニックは少なくありません。ホームページや広告を出していても、来院につながらないという悩みはよくあるものです。
ここでは、集客がうまくいかないクリニックに共通するポイントを整理していきましょう。
認知度が低い
クリニックの集客がうまくいかない理由として、まず挙げられるのが「認知度の低さ」です。
いくら診療の質が高くても、その存在を知られていなければ、患者さんの通院候補にすら入らないのが現実です。特に開院したばかりの時期や、承継によって代替わりしたばかりのタイミングでは、地域住民の目に触れる機会が少なく、集客が伸び悩みやすくなります。
また、情報発信が不足している場合も要注意です。今の時代、検索エンジンやSNS、ポータルサイトなどを通じて医療機関を探す人が増えており、オンライン上での認知拡大は欠かせません。広告やチラシ、看板などのオフライン施策と合わせて、自院の強みをわかりやすく伝える仕組みを整えることが大切です。
ホームページのアクセス数をアップさせる方法とは?7つの方法を紹介!
他院との差別化ができていない
クリニックの集客が伸び悩む原因として、他院との差別化ができていない点も挙げられます。
診療内容や雰囲気、設備などが似通っていると、患者さんは「わざわざそこに行く理由」を見出せません。特に、駅チカや夜間対応などの利便性で他院が優れている場合、自院が選ばれにくくなってしまいます。
たとえば、専門的な治療・女性医師の在籍・バリアフリー対応・待ち時間の短縮など、ほかにはない魅力を打ち出すことが差別化につながります。また、それらの強みをホームページやSNS、チラシなどを通じて、しっかり伝えることも欠かせません。患者さんの目線で「ここを選ぶ価値」が明確になるような情報発信が求められます。
口コミや評価が少ない・低い
口コミや評価の数が少ない、あるいは内容が悪いという点も、クリニックの集客がうまくいかない理由として見逃せません。
特にGoogleマップや口コミサイト、SNSを参考にする患者さんが増えているなかで、オンライン上の評判は来院の決め手となることが多いです。評価が少ないと「本当に大丈夫かな」と不安を感じさせてしまい、評価が低ければ選択肢から外されてしまう可能性もあります。若い世代では特にネットで情報を調べる傾向が強いため、口コミの影響力は小さくありません。
満足度の高い患者さんに口コミをお願いしたり、誠実に低評価へ返信したりと、地道な対応が信頼の積み重ねにつながります。評価の質と量を整えることは、安定した集客の土台となるのです。
予約システムが導入されていない
予約システムが導入されていないことも、集客がうまくいかない大きな要因です。
多くの患者さんは、忙しい日常のなかで「スムーズに診てもらえるかどうか」を重視しています。電話でしか予約できない、あるいは受付時間が限られているとなると、来院のハードルが高くなってしまうでしょう。特に若年層や働く世代にとっては、24時間いつでも予約できるオンライン予約の有無が、クリニック選びの決め手になることも少なくありません。
また、予約状況や待ち時間が可視化されていないと、混雑の不安から来院を避けるケースもあります。近隣の競合クリニックがシステムを取り入れている場合、自院が取り残される可能性もあるため、利便性を高める工夫が欠かせません。
集客の前に確認すべき4つの点
集客施策を始める前に、まずはクリニック内部の状況を見直すことが大切です。いくら広告やSNSで情報を広めても、院内の体制や印象が整っていなければ、来院した患者さんが定着せず、結果的に信頼を失ってしまう場合もあります。
外に向けた発信だけでなく、基本となる院内環境にも目を向けましょう。以下の4つの視点をもとに、改善点がないか確認してみてください。
- スタッフの対応・連携に問題はないか
- 内装や設備に不備はないか
- 医療広告ガイドラインに基づいているか
- 患者目線での説明や提案ができるか
スタッフの対応・連携に問題はないか
医療技術の質が高くても、スタッフの対応が雑だと患者さんの満足度は下がってしまいます。クリニックは医療機関であると同時に、サービス業でもあることを忘れてはいけません。受付や看護師、医師など、すべてのスタッフが気持ちのいい対応をしているか、あらためて見直す必要があります。
たとえば、笑顔がない、説明が不十分、患者さん同士の会話が聞こえる場所で個人情報を話している、などの行為によって印象は大きく左右されます。また、スタッフ同士の連携がうまくいっていないと、対応がちぐはぐになり、患者さんに不安を与えてしまいます。
接遇マナーの研修や院内での情報共有の仕組みづくりを行い、信頼される対応を徹底することがリピーターの獲得にもつながります。
内装や設備に不備はないか
患者さんがクリニックに入って最初に目にするのは、受付や待合室などの「内装」と「設備」です。たとえ診療がしっかりしていても、院内が暗くて汚れていたり、古びた備品が目立っていたりすると、安心感を得られず、通院をためらうきっかけになってしまいます。
壁紙の剥がれや床のシミ、破れたソファなどの細かい部分も、患者さんは意外とよく見ています。また、空気清浄機やキッズスペース、バリアフリー設備など、時代に合った配慮があるかどうかも重要なチェックポイントです。さらに、診療内容に合わせた医療機器がきちんと導入されているかも見直しておきたいところです。
集客を行う前に、まずは「通いたくなる空間」になっているかを確認しましょう。
医療広告ガイドラインを守っているか
クリニックの集客に取り組むうえで見落とされがちなのが「医療広告ガイドライン」への対応です。医療広告は一般の広告とちがい、厚生労働省が定めるガイドラインに従って情報を発信しなければなりません。
特に近年は、ホームページやSNSなども広告と見なされるケースが多く、内容によっては違反と判断される可能性があります。たとえば、治療の効果を過度に強調した表現や、ビフォーアフター写真を掲載する際は、詳細な条件を満たしていないと罰則の対象になるおそれがあります。違反した場合、20万円以下の過料が科されることもあり、知らなかったでは済まされません。
安全かつ適切に情報を伝えるためにも、ガイドラインに沿った表現かどうかを必ず確認しておきましょう。
患者目線での説明や提案ができるか
集客を成功させても、来院後の対応に納得がなければリピーターにはつながりません。特に近年では、医師の一方的な説明ではなく、患者さんとしっかり対話を重ねながら治療方針を決める「インフォームドコンセント」の重要性が高まっています。難しい専門用語を並べるのではなく、患者さんが理解しやすい言葉を使って丁寧に説明する必要があります。
また、選択肢を示したうえで、希望をきちんと汲み取った提案ができているかも重要なポイントです。診療の流れや治療内容について、スタッフ全員が共通認識を持ち、説明マニュアルを整備しておくと、対応の質が安定しやすくなるでしょう。患者目線を意識した説明は、信頼関係の構築につながり、自然と継続した来院にも結びついていきます。
バリュープロポジションとは?作り方を事例をもとにわかりやすく解説タイトル
新規患者を集めるための集客方法
新しく患者さんを呼び込むには、まず「知ってもらう工夫」が欠かせません。
近年では、インターネット検索やSNSで情報収集をする人が増えており、オンライン施策の重要性が高まっています。一方で、チラシや看板といった紙媒体によるアプローチも、地域密着型のクリニックには効果的です。
ここでは、新規集客に役立つ具体的な方法を紹介していきます。
わかりやすく親しみやすいホームページを作る
新規患者の集客において、ホームページは「信頼を得る入り口」として非常に重要な役割を担います。ただ情報を並べるだけではなく、わかりやすく、親しみやすい構成にすることがポイントです。診療内容や診療時間、アクセス方法などの基本情報はもちろん、院内の雰囲気が伝わる写真や、医師・スタッフの紹介を掲載することで安心感を与えられるでしょう。
また、SEO対策も欠かせません。「地域名+診療科」「地域名+症状名」といった検索キーワードで上位に表示されるよう、コンテンツの質や構造を整える必要があります。スマートフォンからの閲覧にも対応したデザインにするなど、ユーザーの利便性への考慮も必要です。
情報発信と検索対策を両立したホームページは、新規患者を得るうえで大きな役割を果たすでしょう。
SEO対策とは?やり方や方法・無料の検索上位表示ツールも解説
SNSを活用して認知を広げる
近年のクリニック集客において、SNSの活用は欠かせない手段です。InstagramやLINE、FacebookやXなどのSNSは、気軽に情報を届けられるだけでなく、患者さんとの距離を縮めるツールとしても活用できます。
たとえば、診療スケジュールの案内や予防医療に関する情報、スタッフ紹介などを投稿すれば、クリニックの雰囲気を身近に感じてもらえます。また、LINEでは予約リマインドやキャンペーン情報の配信ができ、来院のきっかけをつくることも可能です。
重要なのは、ターゲット層に合ったSNSを選ぶこと。若年層ならInstagramといったように、媒体ごとの特徴を活かすことで効果が高まります。認知拡大だけでなく、信頼構築にもつながるSNS運用を意識しましょう。
広告や紙媒体で地域に直接アプローチする
クリニックの存在を地域に広く知らせたいとき、紙媒体を活用した集客は今でも有効な手段です。特にチラシやポスティングは、近隣住民に直接情報を届けられるため、新規開業時や認知度が低い段階で効果を発揮します。
診療科目や診療時間、地図や連絡先などの基本情報に加え、院内写真やスタッフ紹介を載せると、初めての方にも親しみを持ってもらいやすくなります。また、初回限定のクーポンや健康相談イベントなどの特典を添えることで、来院のきっかけづくりにもつながるでしょう。
インターネットに不慣れな世代にも情報を届けられる紙媒体は、オンライン施策と組み合わせることで相乗効果が期待できます。
リピーターを増やすための集客方法
一度来院した患者さんに、再び足を運んでもらうことは、クリニック経営を安定させるうえでとても大切です。新規患者の獲得には時間とコストがかかる一方、リピーターの定着は効率的かつ効果的な集客につながります。
ここでは、患者さんに「また通いたい」と感じてもらえるための工夫をご紹介します。
次回予約の提案・受付での声かけ
クリニックのリピーターを増やすのに最も効果的なのが、診療後すぐに次回の予約を促す声かけです。たとえば、受付時に「◯日後に再診がおすすめです」「この日に空きがありますよ」といった提案があると、患者さんもスムーズに予定を決めやすくなります。慢性疾患や定期検診が必要な方には、通院のペースを具体的に伝えることが、継続につながるポイントです。
また、院内掲示や診察券へのメモなど、さりげない工夫も効果的です。忙しそうな患者さんには無理に勧めず、柔らかい言葉で案内する配慮も忘れないようにしましょう。
LINE・メルマガ・クーポンの配信
リピーターを増やすには、来院後のフォローとして、LINEやメールマガジンによる情報配信が効果的です。診療の案内や季節の健康情報、予防接種の告知などを定期的に届けることで、患者さんの記憶に残りやすくなります。特にLINEは、開封率が高く、通知がリアルタイムで届くため、再来院のきっかけづくりに最適です。
さらに、自由診療メニューに使えるクーポンやポイントが貯まるカード機能の活用で、継続的な来院を促すことも可能です。LINE予約機能を連携させれば、空き状況をそのまま確認できるため、予約までのハードルも下がるでしょう。患者さんの生活に自然に入り込むツールを上手に使えば、集客だけでなく信頼関係の構築にもつながっていきます。
既存患者や離脱患者の分析と対応
リピーターを増やすには、現在通っている既存患者、そして離脱してしまった患者の行動や傾向を正しく把握することが重要です。たとえば、継続通院している方の共通点を分析すれば、今後強化すべきサービスや接遇の方向性が見えてきます。一方、途中で来院が途切れた患者については、どのタイミングで足が遠のいたのか、来院間隔が開いた理由を考えることで、改善のヒントが得られます。
対応としては、定期的なアンケートや、来院が途絶えた方へのフォローメール・LINE配信などが有効です。無理に呼び戻すのではなく「必要なときはまた利用したい」と思ってもらえるような、自然な関係づくりを意識することが大切です。分析と対応を繰り返すことで、患者とのつながりがより深まっていくでしょう。
まとめ
クリニックの集客を成功させるには、外向きの情報発信だけでなく、院内の対応や仕組みも含めた総合的な見直しが必要です。新規患者には認知の拡大と安心感の提供を、リピーターには継続しやすい環境と関係構築を意識することがポイントになります。オンラインとオフラインを組み合わせながら、自院の強みを生かした戦略を展開しましょう。

合同会社楽々Edit 代表 山本 伸弥(やまもと しんや)
新卒でSEOコンサルティング会社に入社し、SEOコンサルタントとして戦略立案から営業、コンテンツ制作まで幅広く従事した後に、合同会社楽々Editを創業し代表取締役に就任。 中小企業から東証プライム企業、ベストベンチャー100まで累計300社以上のSEO改善実績を持つ。 国内大手SEOマーケティング会社10社とデジタルマーケティングカンファレンスも主催している。
\成果が出ていない原因をまとめたレポートをご提供/
\ SEO無料相談会はこちら/
SEO対策の無料相談会を開催中です。転職やクリニック業界などジャンルを横断して競合性の高いキーワードで実績のある弊社にぜひご相談ください。

